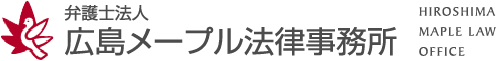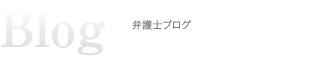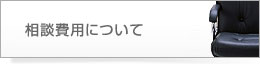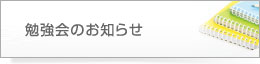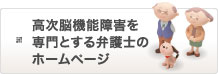職場における悪質クレーム(不当要求、迷惑行為)と働き方改革【№3】
2018.03.05|中井 克洋
(2) クレーム対応する側の体制
次に相手の「誇り」を大切にするのど同じように、クレームに対応する担当者やその組織自身も自分たちの「誇り」を大切にすることが必要です。
悪質クレームをいってくる人はおうおうにして、担当者やその属する組織の「誇り」を傷つける言葉や行動をしてきます。これに対して、こちらの「誇り」を守る体制を整えることが必要です。
「お客様を大切にする」ということは、「お客様のいいなりになる」ということではありません。(1)で述べたように、相手の要求に対してはこちらがきめた範囲の対応をすればよいし、しなければなりません。
もしこちらに何らかのミスがあっても、誰がみても相当な範囲(法と社会通念からみて妥当と思われる範囲)の代償措置をとればよいだけです。それを超えて不相当な言動や行動を受忍しつづけ、さらに相当な範囲をこえて代償措置の要求にまで応じるということになると、担当者や組織の「誇り」が傷つけられます。
人間にとっての最大のストレスとは、「誇り」を傷つけられるということでしょう。それが続くと、担当者にとっては大きなストレスになり、うつなどの精神的問題が発生しやすくなります。
厚生労働省発行の「精神障害の労災認定」(平成23年)においては、仕事によるストレス(業務による心理的負荷)が関係した労災認定に関する「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」が定められました。そのなかでは「業務による心理的負荷評価表」が示されており、その表のなかで心理的負荷の強度が強いとされる業務は労災認定されやすいとされています。
そして、「顧客や取引先から無理な注文を受けた」「顧客や取引先からクレームを受けた」ケースの負荷の強度は「中」とされています。しかしそのなかでも
・通常なら拒めることが明らかな注文(業績の著しい悪化が予想される注文、違法行為を内包する注文等)ではあるが、重要な顧客や取引先からのものであるためこれをうけ、他部門や別の取引先と困難な調整にあたった
・顧客や取引先から重大なクレーム(大口の顧客等の喪失を招きかねないもの、会社の信用を著しく傷つけられるもの等)を受け、その解消のために他部門や別の取引先と困難な調整にあたった
などのケースの負荷は「強」となるとされています。
悪質クレーム・不当要求は無理な注文や重大なクレームであり、その処理に時間的にも心理的にもかなりの負担がかかりますので、その対応は負荷が「強」とされることが多い業務とみてもよいのではないでしょうか。そういえば、2016年夏ころ放映されたNHKスペシャル「シリーズ キラーストレス」でも、ストレスが長期間かかると副腎から抗ストレスホルモン「コルチゾール」が過度に分泌されて、脳の海馬の神経細胞の突起を減少させる、そして海馬は記憶や感情に関わる部位なので、そこが損傷すると認知症やうつ病につながるという可能性が指摘されていました。そしてその典型例として、クレーム対応担当者が紹介されていましたね。
そこで、担当者や組織の「誇り」を守るための体制です。
それは担当者を複数にしてクレーム対応を交代制にするとともに、定期的にそのうちの一部の人を異動するという体制をとることが最も望ましいところです。
クレーム対応の担当者はともすればその処理に長けているとして、同じ人でしかも、一人が長く同じ部署に配置されがちです。確かにオーソリティであって、その人に任せておけば安心かもしれません。
しかしそれは3つの点で問題があります。
・1つはその人がいなくなると苦情処理ができる人がいなくなること
・2つめはせっかくのノウハウが次につながらないこと
・3つめはそのオーソリティ自信も生身の人間であって「誇り」を傷つけられる状態が続けば、キラーストレスにさらされるのでメンタルヘルス上望ましくないことです。
ですからその3つの問題をクリアするためには、担当者を複数にして今回の担当はAさんだけども次はBさん、その次はCさん・・・という交代制にし、さらに重大事案はAさんとBさんがチームで対応するようにする、そして2年やったらAさんは他部署に移ってかわりに甲さんがくる、次の年にはBさんが他部署に移ってかわりに乙さんがくる、というようにしたいものです。
もしそれができるほどの人的基盤がないということであれば、せめて、総務部ないし担当上司にクレーム対応専門担当者をおいて、クレーム対応を受けた部署の担当者と複数で対応できるようにする、という体制をとっていただきたいと思います。
(3) 細かいクレーム対応の現場対応策
実際に私が行う悪質クレーム・不当要求対応の研修会では、現場で相手がこういってくれば、どのように返答すればよいか、などの細かい話もしています。
しかし(1)(2)の基本さえ大切にして、第三者のアドバイスをうけながら、どこまで要求に応じればよいか、を確認さえしていただければ、十分100点満点の対応です。
ぜひともメンタルヘルスや良好な労働環境整備のためにもクレーム対応体制の整備を考えていただきたいと思います。
(おわり)