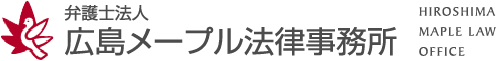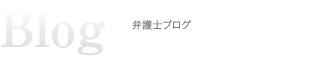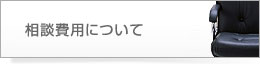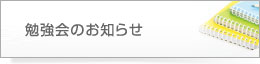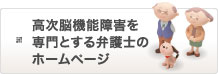「同一労働同一賃金の原則③~不合理性判断の枠組み」
2021.06.14|甲斐野 正行
前回からちょっと間があいてしまいましたが、前回紹介しました、以下の5つの最高裁判決を大枠で整理してみましょう。
①ハマキョウレックス事件(最判平成30年6月1日・民集第72巻2号88頁)
②長澤運輸事件(最判平成30年6月1日・民集第72巻2号202頁)
③大阪医科大学事件(最判令和2年10月13日※民集等への登載は未定?)
④メトロコマース事件(最判令和2年10月13日・民集第74巻7号1901頁)
⑤日本郵便事件(最判令和2年10月15日※民集等への登載は未定?)
旧労働契約法20条は、有期雇用労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより、同一の使用者の無期雇用労働者の労働条件と相違する場合には
・「職務の内容(業務の内容及び業務に伴う責任の程度)」、
・「職務の内容及び配置の変更の範囲」、
・「その他の事情」
を考慮して、不合理と認められるものであってはならない、と規定していたわけですが、①②の最判は、不合理性の判断手法について、大まかには
ⅰ 全体的総合的な判断ではなく、個々の労働条件ごと(例えば、賃金が複数の賃金項目から構成されている場合は、賃金総額の比較だけでなく、賃金項目ごと)に判断する(個別的判断説)(ただし、これも他の労働条件と併せて判断するべき場合があることが否定されるわけではない)、
ⅱ 労働条件の相違が、
a合理的な相違でなければ同条違反とする(その相違が合理的であると裁判所が評価できるだけの根拠となる事情を使用者側が立証できなければ負ける)か、
b不合理な程度に至っていなければ同条違反でないとする(その相違が不合理であると裁判所が評価できるだけの根拠となる事情を労働者側が立証できなければ負ける)か、
については、bで考える、
ⅲ 職務内容及び変更範囲以外の「その他の事情」として考慮する事情を広くとらえ、雇用・人事面での経営判断や労使自治なども考慮する(職務内容及び変更範囲が同じ、あるいはそれほと違いがないからといって、当然に労働条件の相違が不合理になるというわけではない)、
という枠組みを示しました。
(重要な論点としては、もう一つ、不合理と判断された場合の法的効果・救済方法があるのですが、これは後に触れます。)
そして、こうした枠組みは、③~⑤の最判でも基本的には踏襲されているものと解されます。
では、具体的な個別の待遇について次回以降みていきましょう。