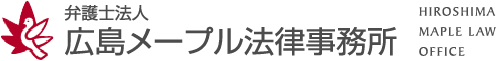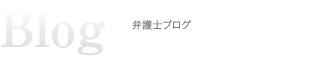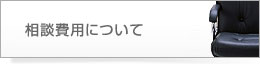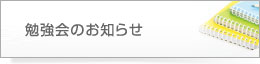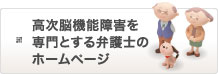職場における悪質クレーム(不当要求、迷惑行為)と働き方改革
2018.02.21|中井 克洋
職場における悪質クレーム(不当要求、迷惑行為)と働き方改革
1 最近、悪質クレームの問題がマスコミなどでとりあげられることが多くなってきました。
私は広島弁護士会や日本弁護士連合会の民事介入暴力対策委員会に長らく所属してきた関係で、暴力団など反社会的勢力からの不当要求に対して対応したり、対策をたてたりすることが専門分野の一つになっています。しかし最近、私が顧問会社などから相談されたり、依頼されたりする不当要求対応のほとんどは、明らかに反社会的勢力とは関係がない人(いわゆるカタギの人)たちによる悪質クレームがほとんどです。
この点、製造業、流通業、総合サービス業の労働組合が加盟している全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟(UAゼンゼン)の流通部門調査(2017年10月)によると、調査対象の流通部門所属組合員(接客対応している販売・レジ業務・クレーム対応スタッフ等)につき
・約74%が来店客からの迷惑行為に遭遇した
・それを受けた人の約90%がストレスを感じた
・約50%が「迷惑行為が近年増えている」と感じている
・約50%が迷惑行為に遭ったとき「上司に引き継いだ」「毅然と対応した」としているものの、約44%が「謝り続けた」「何もできなかった」としている
とのアンケート結果が公表されています。
また、迷惑行為が発生している原因について、ゼンゼンのアンケートでは、
・消費者のモラル低下
・従業員の尊厳が低くみられている
・ストレスのはけ口になりやすい
・消費者のサービスへの過剰な期待
などがあげられています。
そのほかにも権利意識が高まった、SNSなどによってクレームの付け方のマニュアルが流布している、などの要因があるかもしれません。
そして、ゼンゼンのアンケートでは、迷惑行為から自分を守るためにどのような措置が必要かという質問に対して、消費者への啓発活動が約20%という回答となっているほかは、
・企業のマニュアル整備
・企業のクレーム対策の教育
・法律による防止
・迷惑行為への対応を円滑にする組織体制の整備
など、要するに従業員を守るために国や組織がさまざまな対応をしてほしい、という結果となっています。
このように接客の現場で多くの人がクレームをうけて、ストレスを感じており、どう対応してよいかがわからないので企業はその体制を整備してほしいと強く要望している、という実情からすると、それに対して体制を整備することは、企業にとってもワークライフバランスや良好な労働環境の整備を意味します。長時間労働を原因とすると思われる自殺や過労死の事件をきっかけとして、長時間労働対策が「働き方改革」の重要な柱のひとつとなっていますが、悪質クレーム対策も組織の「働き方改革」にとって、大変重要な課題となりつつあるように思います。
私の活動報告でも報告しているように、民間企業だけでなく、行政、病院などさまざまな組織から不当要求、悪質クレーム対策の研修や講演を依頼されることが多くなっています。そして、その研修や講演にはとても多くの人が参加されます。悪質クレーム・不当要求対策が組織運営にとって重要な課題となっていることの証左のように感じます。(続く)