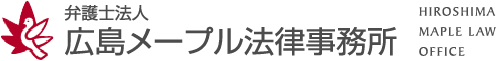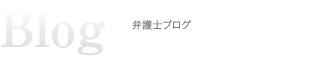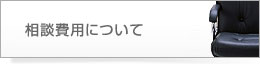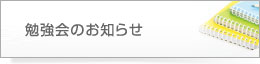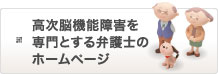平成29年7月7日最高裁判決に関して
2017.07.27|中井 克洋
カープや愛猫などあまり専門家らしい話をしていないので、たまには弁護士らしい話をしようと思います。とはいえ、今回のブログは甲斐野先生、松田先生にもご意見ご指摘をかなり受けながら作ったものですので、私(中井)だけでなく、3人の共同ブログだとご理解ください。
今年(平成29年)6月に弁論が開かれたため、高裁判決がひっくり返ることが予想されており、新聞各紙でもけっこう取り上げられていましたが、今年7月7日に、労働事件の時間外手当に関する最高裁判決が出ました(最高裁判決自体はまだ判例雑誌等には出ていませんので、興味がおありの方は最高裁のHPの判例情報をご覧ください)。
一審の横浜地裁(平成27年4月23日)、二審の東京高裁(平成27年10月7日)および最高裁の判決を読みますと、事案の内容は以下のようなものです。
1 事案
私立病院に勤めていた勤務医Aさんが、解雇の有効性を争ったこととあわせて、病院に対して在籍中の時間外手当を請求した事案です。
ちなみに、社会的には時間外手当の判決のほうが喧伝されましたが、私たちの経験からすると、当事者にとっては、時間外手当よりも解雇が有効かどうかのほうがはるかに重大な問題だったのではないでしょうか。解雇については、地裁、高裁ともに有効とされ、最高裁でも上告棄却されました。
しかしここでは、実務にとても重要な影響を与えると思われる時間外手当の問題にしぼってお話をすることにします。
時間外手当のほうについて事案を整理すると概略以下のとおりのようです。
時間外手当についての労働条件は、時間外規程や雇用契約などにより
・年俸1700万円
本給: 月86万円×12ヶ月=1032万円
役付手当、職務手当、調整手当:
合計34.1万円×12ヶ月=409.2万円
賞与:259万円(本給3ヶ月分相当額)
・週5日勤務
・1日の所定労働時間
午前8時30分から午後5時30分まで(休憩1時間)
・時間外労働の対象となる時間外勤務の対象時間
勤務した日の午後9時から翌日の午前8時30分までの間と休日に発生する緊急業務
・時間外規程に基づいて支払われるもの以外の時間外労働等に対する割増賃金は、年俸1700万円に含まれる
という取り決めがあったようです。
要するに、勤務した日の午後9時から翌日の午前8時30分までの間と休日に発生する緊急業務については時間外手当がでますが、それ以外の時間外手当(勤務した日の午後5時30分から午後9時までの所定時間に働いた分の時間外手当)は年俸1700万円に含まれているということだと思われます。
この合意に基づいて病院からは、午後9時から翌日の午前8時30分までの間と休日に緊急業務をした分について、本給86万円÷月所定労働時間で算定された額を基礎として時間外手当が払われていたようです。
2 各裁判所の判断
一審の横浜地裁判決は、要約すると
① 午後5時30分から午後9時の緊急業務や休日の時間外手当分については、時間外手当の基本となる給与部分と、それ以外の時間外手当分が明確に区別されていないが、その分の時間外手当分については、給料が高いので年俸に含まれるとしてよいだろう。だから、その分は時間外手当を計算しなおして払わなくてもよい。
② しかし、深夜割増や月60時間を超えたときの割増賃金(労基法37条1項で定められたもの)については、時間外手当の対象外になるという明確なとりきめがされていない。だからその分は支払わなければならない。
という内容のようで、②の割増賃金として56万3380円と遅延損害金の支払を病院に命じました。
二審の東京高裁判決もこの内容を是認し、
・本件時間外規程に基づき支払われるもの以外の時間外労働等に対する割増賃金については年俸1700万円に含まれる、という合意は、Aさんの医師としての業務の特質に照らして合理性があり、医師の労務の提供について自らの裁量で律することができたことやAさんの給与額が相当高額であったこと等からも、労働者としての保護にかけるおそれはなく、Aさんの月額給与のうち割増賃金にあたる部分を判別することができないからといって不都合がない。
・したがって、本件時間外規程に基づき支払われたもの以外の割増賃金(上記1審で認容した割増賃金56万3380円を除く)はAさんの月額給与及び当直手当に含めて支払われたものということができる。
として、Aさんの控訴を棄却しました。
それに対して、最高裁は、二審判決に即していうと
・Aさんの医師としての業務の特質、Aさんが労務の提供について自らの裁量で律することができたことやAさんの給与額が相当高額であったからといって、本件時間外規程に基づき支払われるもの以外の時間外労働等に対する割増賃金については年俸1700万円に含まれる、という合意だけでは時間外手当の支払を免れることはできない。
・すなわち、月額給与のうち割増賃金にあたる部分とそうでない部分を判別することができなければ、時間外手当を支払わなければならない。
・月額給与のうち割増賃金にあたる部分が明示された場合でも、それを上回る部分は時間外手当を支払わなければならない。
という判断を下しました。
3 今回の最高裁判決の意味
・時間外手当の算定基礎となる給与部分(以下「基本部分」といいます)と時間外手当分(割増賃金)にあたる部分(以下、「固定残業代」といいます)とは明確に区別すること
・それを明確に区別していたときもその固定残業代に相当する以上の時間外労働をした場合にはその差額分を支払うことも明確にすること
の措置を行わなければ、時間外手当の算定は、基本部分と固定残業代部分の合計を算定基礎として時間外手当が認められる、というのは、現在の裁判例の原則的考え方です。
具体例でいうと、基本給20万円、営業手当5万円という労働条件として、営業手当は残業代がわりだという意識で会社経営をしている会社があるとします。しかし意識だけではだめで、営業手当は固定残業代であり、それを超えた場合には追加残業代を支払うということを明示した取り決めをしておかないといけません。
もしそうしないと、基本給20万円ではなく、営業手当も含めた25万円を基礎に残業代が計算されて、しかも5万円を残業代として支払っているという主張も通らないのです。細かくいうと少し調整が必要ですが、原則的な考え方を説明します。
(1) 基本部分と固定残業代の区別を明確にした場合
営業手当5万円を固定残業分として明示しておけば、例えば所定労働時間が月20日、1日8時間労働とすれば、20万円÷(20日×8時間)=1250円を1時間あたりの単価で時間外手当を計算することになります。
そして、5万円÷(1250円×1.25)=32時間分までは残業代を固定で支払ったものとして扱われます。
そして、ある月にその残業時間分までは残業しなかったときには、繰り越し可能であることを明示しておけば翌月分に繰り越して充当できるということを認めた裁判例もあります(東京地裁平成21年3月27日 SFコーポレーション事件)。
逆にある月に固定分以上の例えば40時間残業すれば、固定残業代に相当する32時間をこえる8時間分の1250円×1.25×8時間=1万2500円につき、追加で支払うことが必要になります。
(2) 基本部分と固定残業代の区別を明確にしていない場合
これに対して、もしも営業手当を固定残業分として明示しておかなければ、時間外手当の算定基礎は20万円でなく、営業手当を加えた25万円となります。
その結果、25万円÷(20日×8時間)=1562.5円が1時間あたりの単価となります。
しかもせっかくの営業手当5万円は残業代の支払分に充当されることはなく、もしも32時間ほど時間外労働をしていれば、1563円×1.25×32時間=6万2520円ほど支払うことが必要になります。
つまり32時間分の時間外労働をした場合、使用者にとっては、営業手当を固定残業分として明示していれば追加の残業代を払わなくてもすんだのに、明示していなければ6万2520円を支払うことになるということです。
今回の最高裁はその考え方に忠実に沿ったものだと思われます。
ただこれまでの下級審の裁判例の中には、年収2200万円以上のような高い給与をもらっており、給与も労働時間に対応するというよりも成果により決められており、ある程度勤務内容も自由に決定できるようなケースについては、労働者の保護に欠けないから基本給のなかに時間外手当が含まれているという合意は有効である、という趣旨の考え方をするものもありました(東京地裁平成17年10月19日モルガン・スタンレー・ジャパン事件)。
また似たような考え方は、時間外手当の対象外となる管理監督者の認定においてもとられてきており、店長などのように管理職のような名称が付された人でも、役職がない人の給与に比べて十分な給与をもらっているかどうかが、重要な判断基準になっています(マクドナルド事件など多数)。
つまり、時間外手当が認められるかどうかについては、十分な給与をもらっているかどうかが裁判所の大きな関心のあるところであり、そこに法律実務家としてのバランス感覚が働いているのだと私たちは感じてきたところです。
その意味でいうと、今回の1審、2審も、そのような考え方に沿ったものといえ、裁判官も同様の感覚の方が多かったのではないかと思われます。
しかしこれに対して、今回の最高裁判決は、給料が高くても、通常の給料の人たちの場合と同じように、どれが基本部分でどれが固定残業代部分かをちゃんと区別して明らかにしないといけないという判断を改めて示したのです。
振り返ってみますと、固定残業代に関する先例的な最高裁判決としては、高知県観光事件判決(最判平成6年6月13日)、テックジャパン事件判決(最判平成24年3月8日)がありますが(今回の判決でも引用されています)、
確かにいずれも給与額自体を検討要素としているわけではありません。
むしろ、テックジャパン事件判決では、労働省出身の桜井龍子判事が、
「労働基準法37条は、同法が定める原則1日につき8時間、1週につき40時間の労働時間の最長限度を超えて労働者に労働をさせた場合に割増賃金を支払わなければならない使用者の義務を定めたものであり、使用者がこれに違反して割増賃金を支払わなかった場合には、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられるものである(同法119条1号)。
このように、使用者が割増の残業手当を支払ったか否かは、罰則が適用されるか否かを判断する根拠となるものであるため、時間外労働の時間数及びそれに対して支払われた残業手当の額が明確に示されていることを法は要請しているといわなければならない。
そのような法の規定を踏まえ、法廷意見が引用する最高裁平成6年6月13日判決は、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別し得ることが必要である旨を判示したものである。
・・・・便宜的に毎月の給与の中にあらかじめ一定時間(例えば10時間分)の残業手当が算入されているものとして給与が支払われている事例もみられるが、その場合は、その旨が雇用契約上も明確にされていなければならないと同時に支給時に支給対象の時間外労働の時間数と残業手当の額が労働者に明示されていなければならないであろう。
さらには10時間を超えて残業が行われた場合には当然その所定の支給日に別途上乗せして残業手当を支給する旨もあらかじめ明らかにされていなければならないと解すべきと思われる。」
と厳格な補足意見をわざわざ述べておられます。
刑罰の根拠になるところだから、時間外労働の時間数と残業代は明確にしろ、というのは確かに強い論拠であり、これだと、給与額の多寡は関係ないといえますし、多いか少ないかは人によって感じ方も変わるところですから、特に刑罰の基準・根拠として考慮要素とするのは適切ではないかもしれません。
テックジャパン事件判決は、最高裁民事判例集(いわゆる民集)には登載されませんでしたので案外実務家の間でもそれほど注目が集まらなかったかもしれませんが、あらためて今回桜井判事の補足意見を読むとその論拠の強さからすれば、今回の判決は予想すべきだったといえるかもしれません。
あるいはまた、勤務医の過酷な労働状況というのが最近の話題になっており、夜間や休日の当直業務が、労働基準法で規定された時間外手当の支給対象となることを認めた最判平成25年2月12日(奈良病院事件)や、厚生労働省でも医師の過酷な労働環境の解消が検討課題となっていることも背景にあるかもしれません。
ただ、そうなると実務への影響は大きいところです。今回の最高裁は、ちゃんと時間外手当を計算しなさいといって、高裁に差し戻しました。
そうすると上で説明したように、基本部分と固定残業代を合計した給与額を基礎にし、しかも固定残業代による充当も認められないわけですから、けっこうな額の支払が必要になるかもしれません。
成果主義で専門的な仕事をして高い給与をもらっている人の時間外手当をどうするかは、現在、政府や野党、連合などのあいだでいろいろ検討がされているようですが、なかなか意見が集約されていきません。
しかし立法がされるまでは、給与の高い専門職を雇用している使用者は、至急、基本部分と固定残業代を明確に区別した給与規程を作り直すことが必要でしょう。
以上