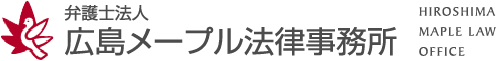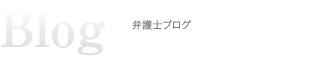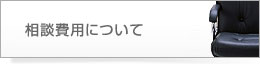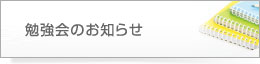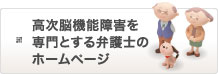第48回勉強会【その1】
2018.02.05|吉村 友和
本年1月12日、第48回合同勉強会が開催されました。
今回のテーマは、前回に引き続き「民法改正」でした。

前回の勉強会では、民法改正の経緯、消滅時効及び瑕疵担保責任の改正点についてお話ししました。
今回の勉強会では、定型約款、保証契約及び賃貸借契約の改正点についてお話ししました。
その内容について、ざっくりではありますが、ブログで取り上げたいと思います。
第1弾は、「定型約款」についてです。
1 はじめに
定型約款という言葉は、現行の民法上は存在しません。
もっとも、私達は、日常生活の中で、約款といたる所で出会います。
カードや会員証を作ったとき、細かい字でびっしりと書かれた約款を手渡されることがあるかと思います。
あれを最後まで全部読む人は少ないと思われます(そもそも目を通すことすらないことが多いかもしれませんが)。
これ自体は契約書ではありませんが、これが契約の内容となり当事者を拘束することがあるのか。
また、契約の内容になるとしても、事業者にとって一方的に有利な条項も含まれている危険があるため、このような条項を規制する必要があるのではないか、という問題がありました。
現行民法では、約款に関する規律がありませんが、改正民法では、「定型約款」という概念が取り入られて、約款に関するルールが新たに設けられました。
2 定型約款の定義
改正民法では、①ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部または一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものを「定型取引」と定義した上、②定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体を「定型約款」と定義しました。
①の「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引」とは、相手方の個性に着目することなく行われる取引のことですので、申込者の中から人格や能力に着目して採用者を決定する労働契約は、①に該当しないことになります。
【続く】